
奥出雲町のホームページを見ていたら、興味深い造形の神社が載っていました。いわゆる木造の建築物の神社でもなく、何か石の板が組み合わさった石が御神体のようです。
鯛の巣山に登った後、その川子神社を参拝しに行きました。
また、山を登った中腹にあるのかと思ったら、自動車ですぐ行ける場所で川子原公会堂という建物の隣でした。
川子神社のお姿
川子神社 島根県仁多郡奥出雲町下阿井1545−6

一見、人工の加工物に見えたが、川子神社の鎮座している山の上の方を見たら、川子神社のような不思議な板のような岩がいくつも見えました。人工の加工物ではなくて、板状節理なんだそうです。
これが自然の造形物としたら、たいへん不思議で神秘的です。
こういうのが、『出雲国風土記』に登場する『神の御門(みと)」というのではないでしょうか?
祭神は玉日女命
奥出雲町のホームページによると、「古老の伝えによれば、阿井川の下流よりワニが恋い慕って登ってくるので、困った玉日女命が大きな石を投げ込み塞ぎ、現在地にお座りになったという」ことらしいです。
川子神社の鎮座しているのは、阿井川の中流であるけれども、同じ奥出雲町の大馬木川にある「鬼の舌震(おにのしたぶるい)」と同様な伝説地だそうです。
ちなみに、『出雲国風土記』の玉日女命が登場する大馬木川も、ここの川と同じく、古名は「あいかわ」(阿伊川)と云ったそうです。
現 阿井川 の古名は「阿位川」
現 大馬木川 の古名は「阿伊川」
鬼の舌震(おにのしたぶるい) 古名 阿伊川にある
島根県仁多郡奥出雲町三成宇根

『出雲国風土記』(733年)の時代には、「鬼の舌震(おにのしたぶるい)」ではなく、「ワニの恋山(したいやま)」でした。
恋山(したいやま)。郡家の正南二十三里のところにある。古老が伝えて言うには、和爾(わに)が阿井村にいらっしゃる神、玉日女命(たまひめのみこと)を恋慕って、川を上ってやってきた。
そのとき、玉日女が石で川をふさいでしまわれたので、会うことができないまま慕っていた。だから、恋山(したいやま)という。
『解説 出雲国風土記』 島根県古代文化センター[編 ]今井出版
私思うに、玉日女命は、奥出雲町の「川の神」だったのではないでしょうか。
露神(つゆがみ)
また、別の伝承では、露神(つゆがみ)と呼ばれる水の神を祭っていたという話もあるそうです。
ここには、大きなほら穴があり、龍神様が住んでおられたということです。
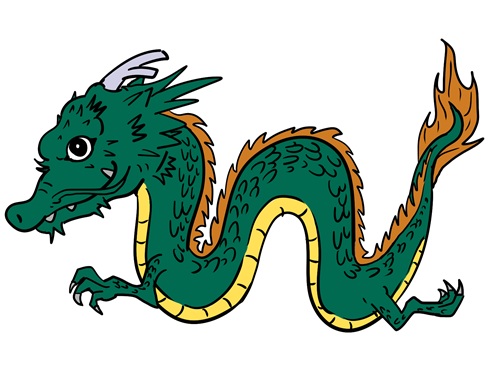
龍神ですから、水の神と同時に「川の神」でもあったと思います。
河童の駒引き伝説
しかし、『仁多町誌』(平成8年)には、川子神社は、河童を祭っており、河童伝説があることが書かれていました。
川子=河の童つまり河童というわけです。

以下、『仁多町誌』の引用です。
昔、川子原の竜が淵にかわこがすんでいた。そのころ、長栄寺の馬が河岸に放牧されていた。竜が淵の近くにやって来たので淵の中のかわこは久しぶりに獲物が見つかり、淵の中へ引き込んでやろうと馬のしっぽをつかんだ。
驚いたのは馬で、しばらく引き合いをしたがついに馬が勝ち、かわこにしっぽをつかませたまま長栄寺の境内まで引きずり帰った。
馬と争ったために頭の皿の水も少なくなり、すでに力つきたかわこは和尚さんに簡単につかまってしまった。
「和尚さん後生ですから命だけは助けて下さい。私が悪かったのです。」と一生けんめいに頼んだ。
「お前が竜が淵にすんで悪さばかりするかわこか、殺してやろうと思ったがそんなに頼むなら許してやろう。だが約束があるが守るか」と和尚さんが言った。
その約束とは、竜が淵の岩に文字を刻みつけ、その文字が消えるまでは決して人や家畜などに悪さをしてはならないということであった。
かわこがどんな約束でも守るというので淵に逃がしてやった。
その後間もなく和尚さんによって岩に文字が刻まれた。それ以来、かわこは河底深くにいて姿を見せず、人畜に悪さをすることはなくなったという。
このことがあってからこの竜が淵を「かわこ淵」と呼び、そのあたりを「かわこ原」「川子原」と呼ぶようになったと伝えている。
『仁多町誌』 仁多町 平成8年3月29日発行
河童も馬も古代 川の神に関係していた
このような河童が馬を川に引き込む話を「河童の駒引き伝説」と言います。馬を川に引きずり込み、たいていは失敗して、河童が詫びてしまう結末になるらしいです。
河童は、民俗学の世界では、柳田国男をはじめとして、河童の正体は水神が零落したものであると考えられています。
柳田国男の民俗学では、山の機織りの女神が、やまんばに転化してしまう話もあります。
元々は川の神、水の神であったものが、長い歴史のなかで懲らしめべき妖怪の位置に落ちぶれてしまったのでしょう。
馬もまた、『続日本紀』 天平三年十二月条に「河伯(川の神)の精」として書かれており、川の守り神でした。
祈雨祈晴の呪術に欠かせず、水と深く関係するがゆえ、奉献されていました。
雨ごいをするときは「黒毛馬」、雨を止むようにするときは「白毛馬」を奉納するのが慣例だったようです。
また、川や湖の祓えの祭祀にも、実際の馬ではなく、馬形も用いられていました。
川子神社に行くまでの橋の上から見える阿井川

河童が住んでいたと思わせられるような雰囲気の川でした。
【参考資料】
・奥出雲町ホームページ 奥出雲遺産 第1回認定
・『仁多町誌』(平成8年)
・マーブルTV『おくいずも 新探訪 ~さらに「奥」へ~』
第25回いわしを見る~大谷の傾城岩・川子神社


